よく使用する湿布には、テープ剤とパップ剤があります。
分かりやすい見分け方は、茶色がテープ剤、白色がパップ剤になります。


患者さん個々で、テープがいい人やパップがいい人がいます。それぞれどんな特徴や違いがあるのでしょう?
目次
粘着力の違い
テープ剤は、薄くて伸縮性があるので、関節などの可動性の高い部位に向いています。しかし、粘着力が強いため、はがす時に皮膚への負担が大きくなり、かぶれやすいです。
パップ剤は水分を多く含み、プルプルしています。そのため、冷たいので患部を冷やしてくれます。粘着力が弱いので、背中や腰など、広くて動きが少ない部位に向いています。その分皮膚への負担が少なく、かぶれにくいです。
投与回数の違い
はっきり決まっている分けではないですが、1日1回貼付は「テープ剤」、1日2回貼付は「パップ剤」な場合が多いです。
もちろん例外はありますよ!
基材の違い
「パップ剤」はもともと“カオリン”という泥状の基剤を使用していましたが、現在の主流は“ポリアクリル酸ナトリウムとアルミニウムゲル”です。網目構造のため、多量の水分や薬効成分を保持しやすい性質があります。
また新に“アクリル系粘着剤”が開発され、基剤と薬剤の相互作用が少なく貼付剤の可能性が広がっています。
「テープ剤」の基剤としては“ゴム系・アクリル系・シリコン系”などがあります。
その他にも貼付剤の全身作用をもたらす構造として『マトリックス型』と『リザーバー型』があります。
薬剤含有マトリックスや放出制御膜等で血中濃度を制御しますが、現在日本で販売されている貼付剤の中で全身作用があるものは、この構造を有する「テープ剤」のみです。
まとめ
テープ剤とパップ剤、どちらを使っても効果はあります。違いは、貼る部位や感触の違いです。
一度皆さんも、使い分けしてみてください♫
参考
- いまさら聞けない「薬」のキホン8「テープ剤」「パップ剤」の違い










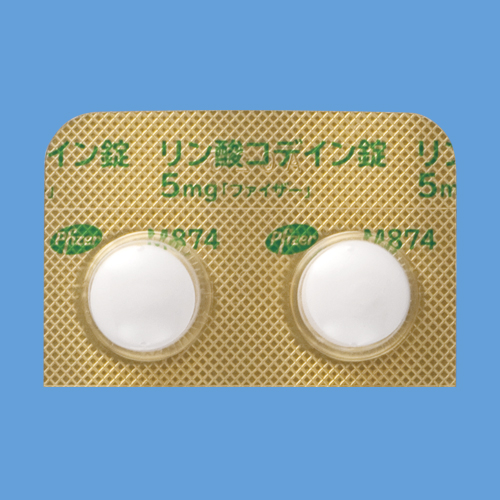








今日は多くの人が使用したことのある、湿布剤の勉強をしようと思います💊