今日は糖尿病治療薬、インスリン抵抗性改善薬の違いについてを整理しようと思います(°▽°)
目次
ビグアナイド薬
肝で糖代謝を抑制し、脂肪分解を促進。また筋の糖取り込みを促進します。
そのほか、消化管からの糖吸収抑制作用もあり、主に体重過多、肥満2型糖尿病患者では第一選択薬となります。もちろん非肥満例にも有効です。単独では低血糖を起こす可能性は低いです。
副作用に乳酸アシドーシスがあるので注意。過度のアルコール摂取は乳酸アシドーシスを引き起こす可能性があるので禁忌です。
副作用で多いのは消化器症状(下痢・嘔吐・腹痛)。
メトホルミン
商品名:グリコラン錠・メトグルコ錠


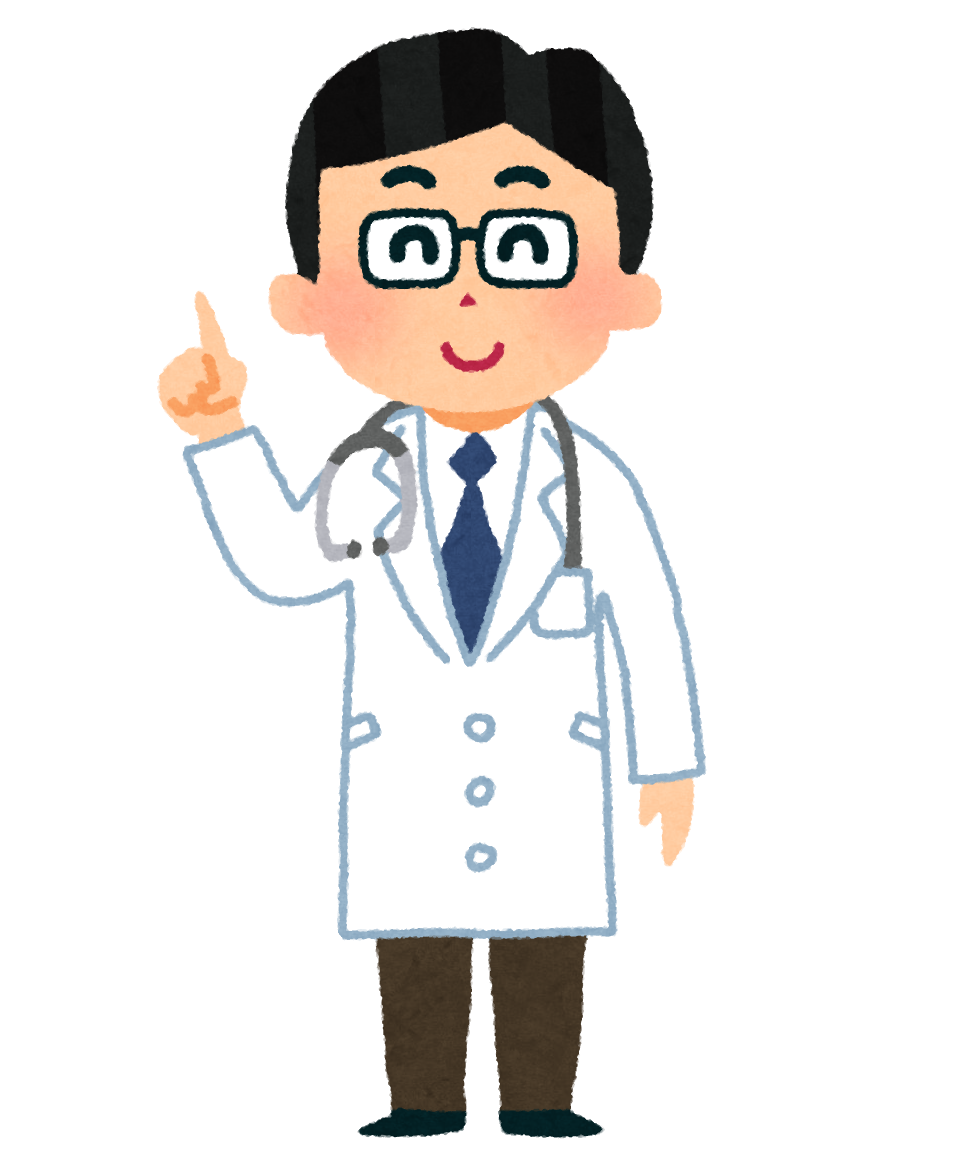
現在の医療ではメトグルコ錠の処方がほとんどですね。
ブホルミン
商品名:ジベトス錠(後発品)
- 適応が「インスリン非依存型糖尿病(SU剤が効果不十分な場合あるいは副作用などにより使用不適当な場合のみ使用)」と厳しいため、使用されることが少ない。
- 腎機能障害軽度・中等度から禁忌。
- 先発品は発売中止なので存在しない。
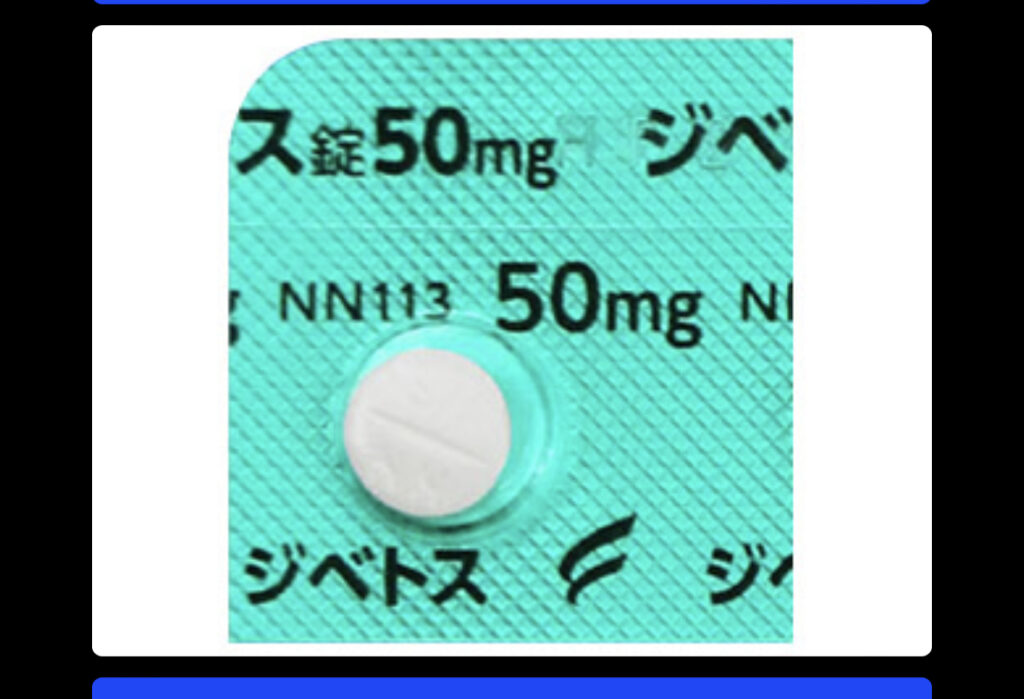
チアゾリジン薬
作用機序は、完全には解明されていませんが、核内受容体のPPARγを刺激してアディポネクチンを増加し、TNF -αと遊離脂肪酸を減少させ、脂肪細胞・筋肉・肝臓に作用して、糖分(グルコース)の産生を抑え、インスリンの効き(インスリン感受性)を改善させることにより、血糖降下作用を発現すると考えられています。
単独では低血糖のリスクは低い。

脳にも働き、食欲を増進させるので体重が増加しやすいので注意です。
商品名:アクトス錠
- 副作用、浮腫の発生頻度は8%程度。女性の方が高頻度で起こる。
- 脂質を改善したり、脳梗塞や心筋梗塞などの血管系イベントのリスク低減効果がある。
- PPARγ刺激により、腎臓のナトリウム再吸収が促され、心不全になる恐れがあるので注意。
- 膀胱癌のリスク、骨密度低下のリスクの報告もされている。
考察
糖尿病治療で欠かせない、インスリン抵抗性改善薬。臨床では、メトグルコ錠の頻度が圧倒的に多いです。
アクトス錠は副作用が気がかりで処方しづらい雰囲気が出ていますね。
今後も糖尿病患者は増加の一途を辿ります。上手に薬も使いつつ適正値を目指しましょう( ´ ▽ ` )ノ
参考
- 新・違いがわかる 同種・同効薬



















ヨード造影剤使用前後は投与中止なので注意しましょう。
シックデイ時は休薬しましょう。